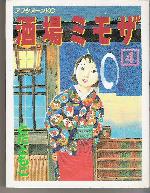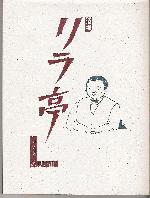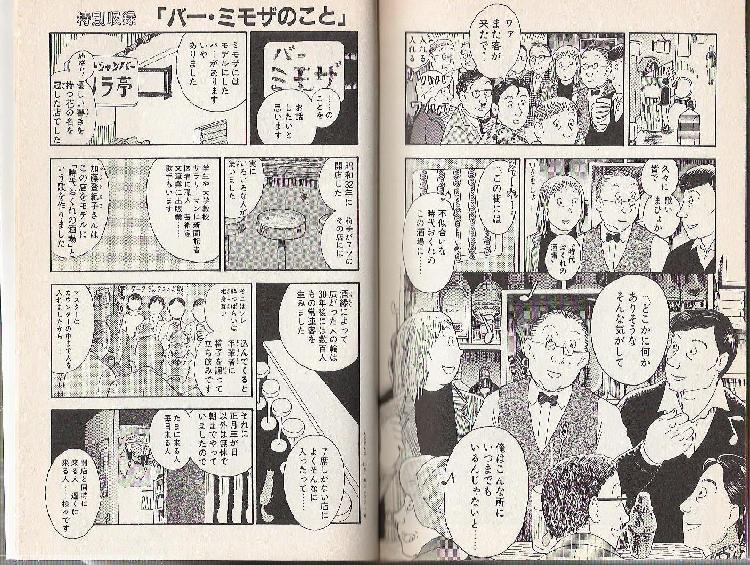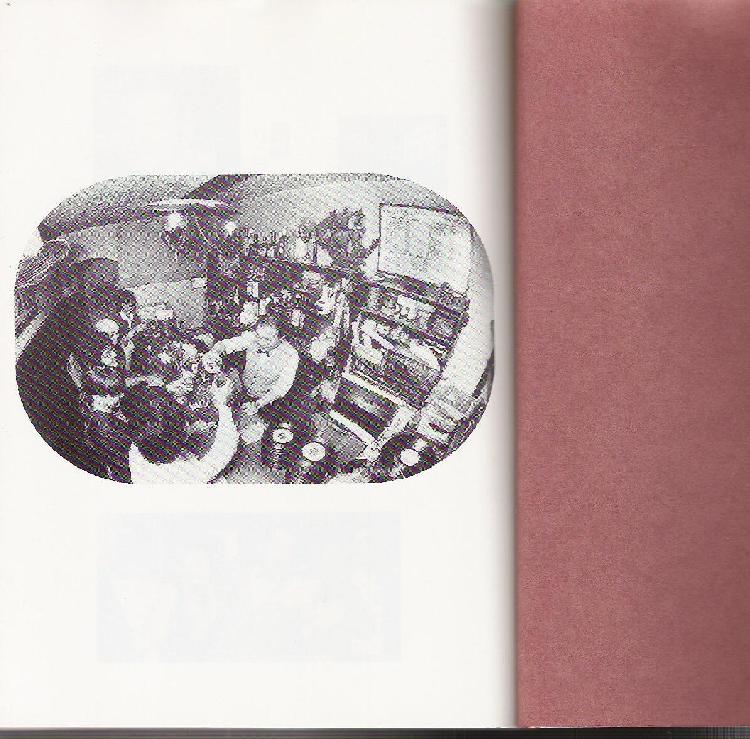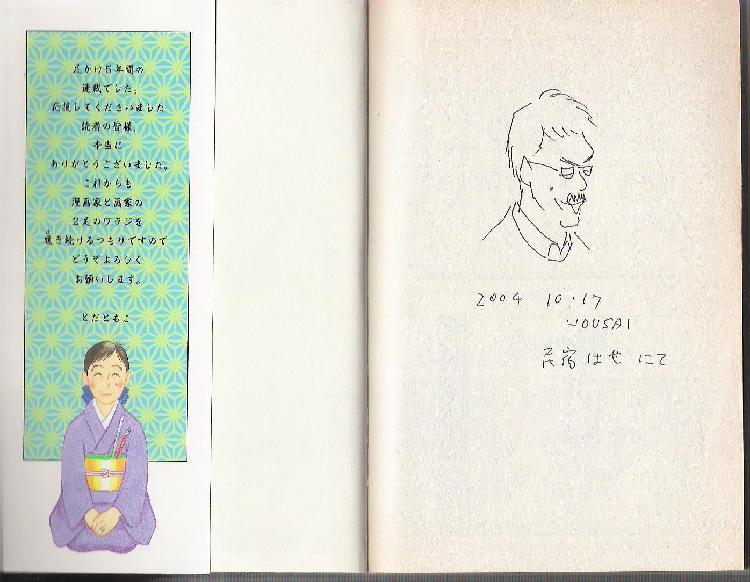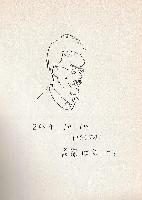男たちには判らない
| アクセスカウンター 1,150,963
新着日記 ・03/03 テスト・10/01 ネオシニアの生きる道 ・09/11 10年前のヨーロッパ旅行 ・06/16 ネオシニアの生き方 ・09/24 首都圏からリゾート地への旅をする 2013 ・09/14 首都圏の旅/2013晩夏/パート2 ・09/07 関西人、東京に現る 千葉南房総と首都圏の旅 ・07/07 愛地球博跡地と伊良湖岬 ・05/28 瀬戸田、耕三寺から大三島へ ・05/28 尾道から向島、因島へ 新着コメント ・kotaro 1970・wahei 1970 ・kotaro 【保存版】靴の修理屋さん ・lancista 【保存版】靴の修理屋さん Calendar
User定義カテゴリ ・日記(68)・くるま全般(41) ・おんがく(1) ・中古カメラ病(4) ・鉄は直らない(8) ・旅日記(47) ・都市風景(22) ・長屋暮らし(4) Links
・ラテンでゴメン
自動車のこと中心に小生が書いています。
・家ieご近所にある、ギャラリーカフェ。毎週木〜日で12時〜18時営業。
・ヘイアドウード市内にある、ちょっと面白いセンスした、服の直し屋さん。男性の方ですが感性の豊かな店です。
お勧めBLOG
・e-konの道を行く
鄙なる道を訪ね、日本の忘れてきた風景を思い起こさせてくれます。
・ゼロから始める輸入中古車ライフ一昔前の輸入車を実用的かつ趣味で乗ろう。ノウハウや知識が満載のブログ。
・あのコルトを狙え!旧い三菱コルトに乗り時間旅行するホテルマン。熱海など昔の観光地ガイドは秀逸。
・なのはなテレビ80年代のアイドル歌手を温故知新で再評価など、丁寧な文体に好感が持てます。
・地球に優しい車生活豊中の私のお世話になるショップさんがブログを始められました。スタッフの内、娘さんが書いているようです。女性と自動車工場の家族を見た視点がなかなか面白く創意工夫で車を治していく工程も面白いです。
アーカイブ ・2017年03月(1)・2014年10月(1) ・2014年09月(1) ・2014年06月(1) ・2013年09月(3) ・2013年07月(1) ・2013年05月(2) ・2013年03月(1) ・2013年01月(1) ・2012年12月(1) ・2012年11月(1) ・2012年09月(1) ・2012年08月(1) ・2012年05月(1) ・2012年04月(1) ・2012年03月(1) ・2012年02月(2) ・2012年01月(1) ・2011年12月(1) ・2011年11月(1) ・2011年10月(2) ・2011年09月(2) ・2011年08月(3) ・2011年07月(2) ・2011年06月(2) ・2011年05月(3) ・2011年04月(1) ・2011年03月(2) ・2011年01月(2) ・2010年12月(4) ・2010年11月(5) ・2010年10月(2) ・2010年09月(2) ・2010年08月(3) ・2010年07月(3) ・2010年06月(4) ・2010年05月(3) ・2010年04月(4) ・2010年03月(5) ・2010年02月(9) ・2010年01月(4) ・2009年12月(3) ・2009年11月(2) ・2009年10月(4) ・2009年09月(3) ・2009年08月(7) ・2009年07月(4) ・2009年06月(4) ・2009年05月(4) ・2009年04月(7) ・2009年03月(7) ・2009年02月(2) ・2007年06月(3) ・2007年05月(7) ・2007年04月(5) ・2007年03月(7) ・2007年02月(5) ・2007年01月(6) ・2006年12月(4) ・2006年11月(8) ・2006年10月(3) ・2006年09月(9) このブログは
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||